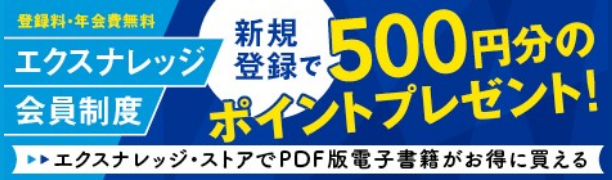ホテルのリノベーションを数多く手がける佐竹永太郎氏(STAR)。その事例を紐解いてみると、用途・デザインの多様性に気がつきます。「当社のミッションは、〝クライアントの課題を美しさで解決する〟ということ。言い方は少し乱暴かもしれませんが、建築家にありがちな作品性を押し付けるということではなく、クライアントの問題意識に寄り添った最適なデザインを提供するように、常日ごろから心がけています」(佐竹氏)。
したがって、STARには標準化された設計手法というものが存在しません。言わば、佐竹氏の仕事は、単なる建築の設計ではなく、建築をコアとする、クライアントのリブランディング(ブランドの再構築)ということになるでしょう。その作業を建築という視点から、法則として落とし込むと、以下のように説明できます。
1 外観の美しさを引き出す
外観の化粧直しは、ホテルの個性を世の中に広く訴えかける意味で最も重要な要素。改修の場合は新築とは異なり、外観をゼロから構築することはできませんが、たとえば、リゾートホテルへの再生として、客単価の大幅な向上を狙うのであれば、外観の刷新に費用と手間をかけましょう。費用と手間がかけられない場合も、外壁の再塗装や格子の取り付けなどによって、くたびれた外観に美をもたらすことが可能です 。さらに、建物が密集する地域では、建物周囲の状況を正しく見極め、人の目に触れやすい下層部分のみをデザインし、上層部分には手を付けない、という割り切った考え方を採用するケースもあります。

海の眺望と温泉を売りとする、ヒルトップのスモールラグジュアリーホテルとして再生した「INFINITO HOTEL&SPA南紀白浜」。海外のリゾート地にいるかのような感覚を呼 び覚ますファサードのデザインが印象的

“かんぽの宿”をミドルクラスの旅館として再生した「指宿温泉 こらんの湯 錦江楼」。国内からの観光客や地元(鹿児島県指宿市)の風土を意識して、外壁をブラウンで 再塗装し、地元産材による格子でアクセントをつけた

ワンルームマンションを外国人観光客向けデザインホテルとして再生した「桜スカイホテル」。目抜き通りに立地する建物に配慮して、ファサード全体に手を加え、上層部分にはオリジナルのサインを取り付けた

ウィークリーオフィスを外国人観光客向けデザインホテルとして再生した「椿ホテル」。予算が限られていたほか、建物密集地で、上層部分が通行人の視線に触れにくいため、下層部分のみを、瓦屋根の軒が織りなす“和”の空間に仕立て上げた
2 共用部分で物語を印象づける
レセプションのある共用部分は建物内の印象を大きく左右する重要な部分。ホテルのターゲット層を具体的にイメージしながら、内装のデザインを整えましょう。たとえば、〝和〟のデザインといっても、日本人が抱く〝和〟のイメージと、外国人が抱く〝和〟のイメージには多少のギャップが存在します。その違いを意識して内装のテイストを変えるのも肝要。前者では木材などを取り入れながら素朴に、後者では浮世絵などを取り入れながら派手に装うのもよいでしょう。遊休状態のマンションを用途変更してホテルに再生する場合は、“マンションの容積率緩和”[※]という規定を逆手にとって共用部分を開放的にする、という手法もあります。

「指宿温泉 こらんの湯 錦江楼」のレセプション。内装全体を落ち着きのあるブラウン系でまとめ、外観と同様に、木の格子でアクセントを付けた


保健所の規定で設置した浴槽を共用部分のディスプレイとして活用した「椿ホテル」。銭湯のような設えとした

“マンションの容積率緩和”の規定を逆手にとって大きな吹抜けをつくり、開放的な共用部分とした「桜スカイホテル」
※ 共同住宅は容積率の緩和規定が多く、エントランス・共用廊下を床面積に算入しなくてよいが、宿泊施設ではエントランス・共用廊下を床面積に参入する必要があり、容積率が増える。マンションを宿泊施設に用途変更する際、上階の床をなくして吹抜けとすれば、容積率対象の床面積を減らせ、求められる容積率に適合できるうえ、開放感や高級感が演出できる
つづく