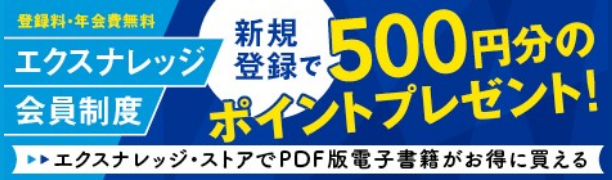かたちから考える 飯塚豊
「間取りを優先すると住宅は美しくならない」そう言い切るのは、ベストセラー『間取りの方程式』(エクスナレッジ)や『新米建築士の教科書』(秀和システム)の著者の飯塚豊さんです。間取りを優先にすると立面や断面が後回しになり、美しさだけでなく構造や住みやすさにも支障が出てくるからです。飯塚さんは周辺環境や気候風土、敷地条件にあった「かたち」を考えることから始めるといいます。もし、あなたが間取りから考えていたら、まずは設計の手順を見直してみるとよいでしょう。
下記は、飯塚さんが考える「美しく設計するための正しい手順」です。全部で10項目ありますが、最初の5つは準備段階。残りの5つは、準備段階で整理した情報を具体的なかたちに落とし込む、いわば解法(設計)。
飯塚さんが考える美しく設計するための正しい手順
- 構法を決める
- 素材を選ぶ
- 事例を調査する
- テーマを設定する
- 条件を整理する
- 屋根からかたちを考える
- 中間領域のかたちから考える
- 窓の配置を検討する
- 架構を想定する
- 間取りを描く
こうして導き出されたかたちによって、間取りも魅力的になっていくのです。

『伊礼智の住宅デザイン学校 10人の建築家が教える設計の上達法』p14
余白から考える 丸山弾
東京都中野区で生まれ、現在も中野に事務所をかまえる丸山弾さんは、子どものころから住宅密集地や細い路地を歩くのが好きだったといいます。どんなに建物に囲われていても、ふと視線が抜ける場所はあるもので、その変化を楽しむ感覚が都会暮らしの中で育まれていきました。そんな丸山さんが設計で大切にしているは「余白」。敷地を見て、余白を探しながらプランニングするそうです。視線の抜けも余白が生み出すものの1つ。どんなに住宅密集地でも余白をあきらめない丸山さんの設計は、のびやかで落ち着きのある空間をつくりだします。

石神井の家(2016年)

『伊礼智の住宅デザイン学校 10人の建築家が教える設計の上達法』p36
身体スケールから考える 八島正年
大きな空間=気持ちのよい空間とは限りません。それぞれの床面積にあった天井高さがあるし、使う人にとって居心地のよい大きさがあります。八島正年さんは、小さな保育施設の仕事をきっかけに「身体スケール」を大切にするようになったといいます。それは、大きな木の下に四畳半ほどの園舎で、子どもたちの「身体寸法」と「動作寸法」の2つのスケールからデザインを解いていったそうです。園舎は、大人にとっては狭く、使いづらいサイズでしたが、子どもなら10人入っても遊べる空間です。「身体スケールをきちんと考えられれば、空間の大小に関わらず心地よい空間ができることを学んだ」と八島さん。無理のない、端正な佇まいは、このような視点から生み出されるのでしょう。

『伊礼智の住宅デザイン学校 10人の建築家が教える設計の上達法』p130
アプローチの仕方は、建築家によってさまざまですが、間取りから考えないことで周辺環境や住まい手の個性に合った住宅が生み出されているようです。本記事は、書籍『伊礼智の住宅デザイン学校 10人の建築家が教える設計の上達法』(エクスナレッジ)の一部を再編集してまとめたものです。もっと詳しく知りたい!と思った人は、ぜひ読んでみてください。