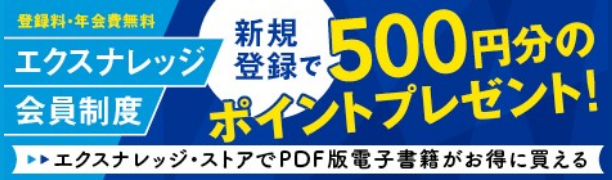〝二世帯化リノベ〞を今後のトレンドに
実際に住み始めたのは2020年の6月。住まい手の実感としては、冬の居心地が圧倒的によい。冬は、やってよかったなあとしみじみ実感します。建物内の温度差があまりないので、暖房(ルームエアコン)の温風を強く吹き出す必要がなく、じんわりとした温かさが感じられます。暖房に頼らなくとも、朝が寒いということは一切ありませんね。
引っ越した時期が、ちょうど、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発令されていたさなかでした。それまでは出張ばかりでほとんど自宅にいなかったのですが、家にいる時間が一気に増えた時期でもあり、リモートワークの環境としても申し分ない、と感じています。
建物のどこにいても緑豊かな庭とつながる

防水バルコニーには新規にウッドデッキを敷設し、アウトドアリビングに。天井も木質系の「軒天12 YL141P」(ニチハ)で仕上げている
一方、夏は、2階で過ごすとやはり暑さを感じます。開口部が多いので、窓を開ければ通風によってそれなりの涼しさは得られるのですが、屋根からの輻射熱で空間全体の温度が上昇してしまうのです。天井裏には140㎜厚の断熱層を形成しているのですが、屋根の外側からは断熱をしていませんからね。
したがって、次の目標は屋根(化粧スレート)の断熱・気密性能強化です。ボード系の断熱材で屋根の外側から断熱を行い、建物全体の断熱性能をさらに高め、少なくともHEAT20G2レベルまで性能を高めたいと考えています。太陽光発電モジュールの搭載も視野に入れています。
増田奏氏の原設計を生かした1階

両側に天井いっぱいの開口部がある1階のLDKは、ほぼ原設計のまま。緑の中に突き出したような感覚が得られる。三角形のサッシは「K-WINDOW」(栗原)

増田氏が設計したⅡ型の造作キッチンは、大島氏の母が約30年間にわたって愛用したもの。幅が3,450㎜と長めで、作業スペースやシンクは通常よりも広く、使い勝手がよい。床断熱を行うため、いったん撤去して再設置

木製防火戸「KG94F(O)-1021」(ガデリウス・インダストリー)を開くと、奥行きのある玄関土間越しに坪庭が広がる
関連記事:“住まい”の設計は無目的を旨とすべし―増田奏―はこちらから。
最後に、自邸のリノベーションを通して、私は実際に暮らしながら1つの仮説を検証することができました。それは、〝二世帯化リノベ〞が、エネルギー効率の改善や高齢者福祉・児童福祉といった複合的な問題を解決できる有効な選択肢であるということです。とりわけ、エネルギー効率については冬、2人で月約6万〜7万円かかっていた光熱費が、現在では5人で月3万〜4万円に圧縮できています。経済情
勢も不透明ななか、これからの家づくりを考えると、一戸建ての新築を1世帯で購入するというのは負担が大きい選択肢。日本の人口が減少するなか、次世代の税負担を考えれば、いつまでも公的な補助金に頼りきるわけにもいきません。
ブルースタジオでは、小田急電鉄さんとの仕事を数多く手がけていますが、小田急線沿線には「大島邸」のような魅力のある中古住宅がたくさんあるので、郊外の〝二世帯化リノベ〞を積極的に提案していきたいですね。働き方も変わり、家で仕事をするのが当たり前の選択肢になっているなか、〝二世帯化リノベ〞は賢明な選択肢になると考えています。
語り=大島芳彦(ブルースタジオ)
写真=平林克己 / 協力=増田奏(S M A)+『住まいの解剖図鑑』