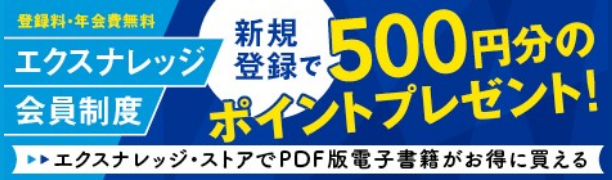大野博史氏による建築知識実務セミナー「木造の多様な空間における梁の構造設計」。具体的には、梁の役割や組み方の工夫について実例を交えながら解説が進められました。
まずは木造の梁を設計する場合にポイントになる”たわみ”について解説。
続いては床面積当たりの梁の負担荷重について。梁を水平方向に敷き詰めるマッシブホルツについても説明されています。
続いては「建築知識」のtwitterでもバズった”レシプロカル構造”(持合い構造)について。A4用紙と箸、コップを用いて構造の原理を解説しているほか、狭小敷地で短い梁材しか建て込めない条件で同構造を採用した「DAYLIGHT HOUSE」(設計:保坂猛建築都市設計事務所)について解説しています。
続いては梁の設計で重要な指標となる断面二次モーメントについて。梁幅よりも梁成を大きくすると、断面二次モーメントが大きくなり、大スパンが可能になる、という内容を説明しています。その原理を応用したのがトラス梁で、実例として「日本平夢テラス」(設計:隈研吾建築都市設計事務所)も紹介されています。
最後は登り梁で大スパンを飛ばす方法。単純梁ではなく、複数の梁を三角形に組むことで短い材でも大スパンを実現できるというもの。ただし、水平方向に開く(通称:スラスト)現象があるので、その対策について「むく保育園」(設計:手塚建築研究所)を引き合いにしながら説明しています。
MEMO “レシプロカル構造“、建築知識のTwitterでバズる!
A4用紙と箸、コップで表現した“レシプロカル構造”。「建築知識」でtweetしたところ、マニアックな内容ながらも思わぬ大反響。数多くのリツィートや“いいね”を獲得しました。身の回りのものを用いて構造の本質を表現する」という面白さや、「1つ1つは弱い材料でも組み合わせ次第では強い骨組みを構成できる」という日本人の琴線に触れる工夫が直感的に伝わったのかもしれません。
なかには実際に真似をした人も。“構造”といえば設計者も苦手とする人が多いかもしれませんが、ちょっとした工夫でより直感的に理解できるようになり、意匠と構造のバランスが取れた提案ができるようになるでしょう。